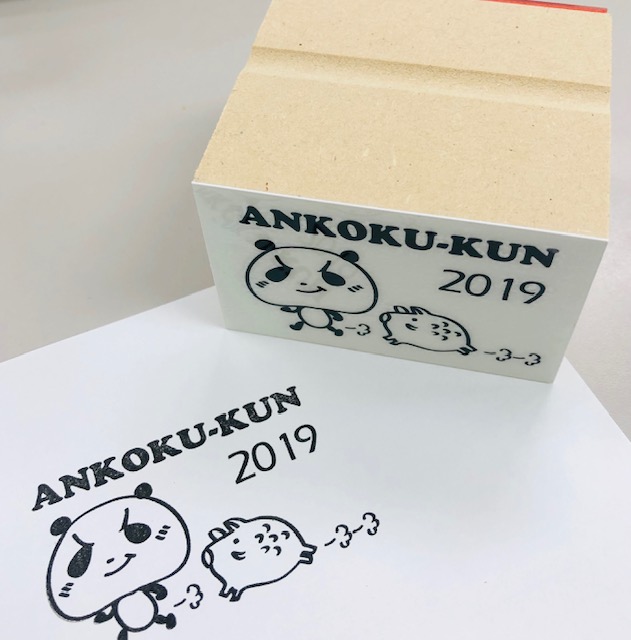社長ブログ
株式会社アイネット
みなさん、こんにちは!
今日は「自分が誰かをがっかりさせているかもしれないこと」について書こうと思います。会社の代表歴が長くなってくると、色んな人から相談を受けることもじわっと増えてきて、たとえば「管理職になったけど、みんながついてきてくれない」とか、「採用したいけど、内定を出しても応諾してくれた人が一人しかいない」とか、「新人が数年ぶりに配属されるけど、どう接したらいいか分からない」とか、私自身も一度は考えたことがあるようなことなども相談されたりします。
そんなお悩みのうち、とくに「人がついてきてくれない」ということについて今日は書いてみます。
これについては私は人よりたくさん考えてきたのですが、それは、つまり「山本さんには誰もついて来ないよ」と面と向かって人生で三回ぐらいは言われたことがあるからなのです。
会社の代表になるときも言われましたが、経済団体の倉敷地域の会長になるときなんかにも言われました。もちろん、言われたらショックですが、じゃあ本当の本当に私に人望が無かったかというと、一方では私を推薦する人たちなどもいたわけで、言った人の感情などが含まれていたのだと、いまなら分かります。
ただ、「あなたには誰もついていかない」と私を評価してくれた人が何人かいたお陰で、私自身は「自分のどこがいけないのか」ではなくて「どうすれば人がついてきてくれるか」についてめちゃくちゃ考えることができたわけです。
そこで考えたことの中のひとつが「人がついて来ないというのは、組織の多くの人をがっかりさせているのかもしれない」ということでした。
自分の所属組織の代表に対してがっかりすることがあるとすればどんな時でしょうか。
大勢の人の前でしゃべるのがめちゃくちゃ下手だったら、私ならがっかりするだろうな。と思ったので、スピーチを習いに行きました。
字が下手だったら、私ならがっかりするだろうな。と思ったので、筆ペンを習いに行きました。
ケチだったらがっかりするだろうな。と思ったので、もらい物は独り占めしないようにしたり、投資と思ってお金を惜しまず払う機会をつくるようにしました。
そういう風に自分ががっかりされるような原因を探して、一つ一つ改善してみたわけです。そうやって、小さながっかりを改善して私がまとう評価の空気を変えることで、自分へのマイナス評価は一気にプラスにひっくり返せるという体験もたまに経験してきました。
逆にどうにもならないこと、たとえば、女性であるとか、子育て中で充分に残業できなかったこととか、年下というだけで生意気に見えることについては、いま思えば悩んでも意味がなかったことでした。
いまもし、「人がついて来てくれない」と悩まれている管理職のかたがおられたら、一気に状況をひっくり返すことを考えずに、自分を俯瞰して出てくるキーワードにちょっとずつ取り組んでみるのもいいかもしれませんね。
では、寒くなってきましたのでみなさんご自愛ください!
みなさん、こんにちは!
以前、「1on1(ワン・オン・ワン)」について少し書かせていただきましたが、先日、社内で次年度の「1on1」の進め方について、引継ぎや改善点を話し合いました。一対一の閉じた場で行われるので、あまり「こうするべき」と決めてしまわず、それぞれの部下の人の個性や二人の関係性に合わせたり、その場の流れで内容を変えたりするのが良いのですが、ひとつだけできるだけ付け加えて欲しい点を私からお願いしました。
それは、
「会社が考えていること、大事にしていることを意識してもらうように伝え続ける」
です。
弊社は関東にも何人か社員がおり、距離が離れているため、これまでも何度か「本社の考えていることが分からない」という意見が出ていました。メールなどで何度も通知していても届いていないと感じることも多々ありました。なので、私自身が関東に行った際には、会うたびに考えを説明したり、変更があれば変更を伝えたりするように意識しています。
「会社が何を考えているか」は、「経営トップが何を考えているか」と混同されがちですが、「会社の考え」のポイントは内容と根拠がきちんと上層部と共有されて、上層部がさらにその下に全く同じ気持ちを持って説明できるかだと思います。
現在、関東にオフィスを構える計画を練っています。それは関東のメンバー全員と共有されており、その中でも立ち上げ時に役割を担うことになる人がオフィスを構えることに納得していたり、オフィスができたあとで自分がどう関わるかをイメージできるのが一番大事です(地方から関東にオフィスを出して失敗した会社の事例もたくさん他社さんから聞いておりますので…!)。そのためには何度も対話を重ねないとダメだなとつくづく思います。
私、SNSで会社のトップの人が発信するときにけっこう大事だなと思うポイントは、「どれだけ自社の人と対話してるのか」が分かるような発信をしてるかどうかだと思っています。他社の人とイベントで交流してたりする様子とか、自社の商品をイベントで展示したとかっていう発信は多いと思うのですが、たとえば、「昨日、入社三年めの総務の〇〇さんが『こういう改善はみんな喜ぶんじゃないかなあ』という話をしてたから、ちょっとおもしろいなと思って検討してみることにした」なんていう発信をするトップの人がいたら、その会社はすごく良い会社だと思うんですよね。
うちはそんなに大きな会社ではないのでわりと対話し易い環境だとは思いますが、それでもまだまだ足りているとは思っていないので、いろんな機会に織り込みながらもっともっと社内の対話を増やしたいと考えています。
みなさん、こんにちは!
知り合いの技術者のだいくしーさんがちょっと悩みというか、これからどうしていこうかなというような気持ちを正直に書いておられました⇩。
私自身もいろいろ思うところはあるのですが、他にもたくさんの方がアドバイスをされているでしょうから、ここはひとつ、同じように悩んで経験のある私が技術者としての師匠でもある夫に聞いた話も交えてエントリを書きたいと思います。
私の夫は、私が初めてIT業界に入った時の上司でした。当時は、まだWindowsはなくてMS-DOSの時代で、私が初めて学んだ言語はC言語でした。当時は夫は35歳。夫の経歴ですが、もともとは電気関係の仕事をしながら趣味のマイコンを触っており、あるとき仕事を休んで趣味のロッククライミングで一ヶ月オーストラリアに行った合間に『プログラミング言語C』(有名なK&Rの)を読んで帰国して、そのまま30歳でこの業界の門戸を叩き、いきなりプログラミングの仕事に就いたときに「この業界はチョロいな」と思ったそうです(笑)。
初出社で会社に行ったとき、床に寝袋で寝ていた夫がむくりと起き上がったのが忘れられません。古き時代のプログラマのイメージそのままでした。
当時、C言語は流行り始めでしたが、まだ多くの人は開発経験が少なく、今のようにインターネットなどない時代でしたので、当初は夫は社内をけん引してプログラミングをしていましたが、ある時から部長になり、コードはあまり書かなくなりました。昇進した当時は、机の上に足を上げて技術書をずっと読んでいました。それから何年かして、そのときにいた会社を辞め、再びプログラマに戻り、本来であればアイネットを継ぐ選択肢もあったのですがきっぱりと断り、今もまだ現役のプログラマを続けています。
さて、そんな夫に当時の「コードを書かなかった」時代についてちょっと訊いてみました。
(私)「一時期、部長になって、来る日も来る日も技術書ばかり読んでたじゃない?あれって、コードを書かないことでの不安はなかったの?」
(夫)「なかったなあ。あの時は過渡期だったからね。MicrosoftがGUIを発表したばかりで、それをちゃんと押さえようという気持ちが強かったから」
(私)「逆に自分が先んじて新しい技術を把握しておきたかった?」
(夫)「そうそう。そんな感じ」
そういえば、その後結婚してからも、夫は「この技術は押さえておこう」という技術は、分厚い言語の仕様本なども、毎日来る日も少しずつ読んでいた覚えがあります。また、大晦日に除夜の鐘を聴きながら趣味のコードを書きながら新年を迎える、ということをずっとやっていました。
さて、夫が経営などやりたくないといって逃げてしまった後のアイネットで、私は経営という事に携わりながら、社長でいつつ技術者を自称するのはとても難しいことを実感しています。むしろ、社長が技術者であると前面に出すのはよくない。私の軸足は経営に載っているべきであって、技術者に寄ってしまってはいけないと思っています。私がやるべきことは技術者的判断ではなくて経営判断だからです。一方で、技術者を理解するためにはどうしたらよいか。コードを書く量は圧倒的に職業的プログラマに比べて少なくても、こつこつと夫がやっていたように技術書を読み、部下の人よりコードが書けなくても、部下の人に訊きながらでもコードを書くことを理解し、寄り添い、自分より優れた技術者を輩出するための環境を整え続けることしかないと思っています。
そこに派手な成果はないかもしれないけれど、今でも私が技術の落後者として絶望せずにこの仕事に関わり続けられているのは、毎夜、分厚い技術書を、その技術の提供する哲学を理解するために読み続けていた夫をずっと見ていたからではないかと思っています。
結局のところ、夫はマネジメント職におさまるよりは、コードを書き続けることを選択した人だったということに尽きるかとは思いますが、悩める技術者の参考になればと思いこのエントリを書かせていただきました。
みなさん、こんにちは!
先日、岡山経済同友会の定例幹事会で青柳正規氏の『2020年オリンピック・パラリンピックにてういて -岡山に期待するもの-』という演題の講演を聴いて感じたことについて書きます。
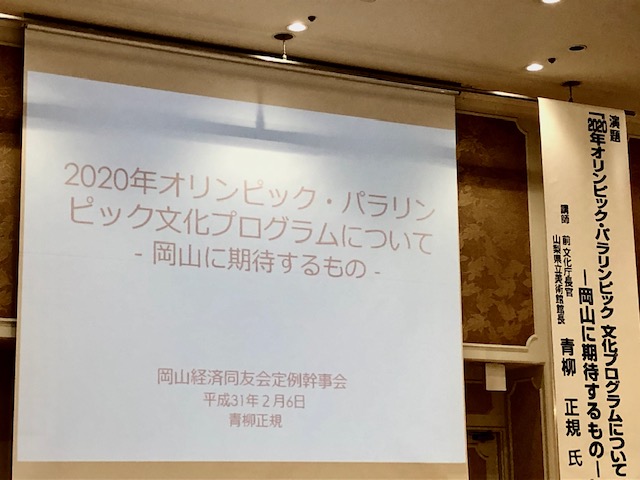
青柳正規氏は古代ローマ史が専門で、元文化庁長官、美術館関係の重職を兼務しておられ、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の文化・教育委員会の委員長もされています。
今回はそういう視点からお話をくださりました。
特に、私も知らなかったのですが、リオ+20(リオプラストゥエンティ)という会議で、「本当の国の富とは何か、どんなストックがあるか」をGDP以外で試算したところ、日本は当初、アメリカに次いで2位だったそうです。「生産資本」「自然資本」「人的資本」で、特に日本が突出しているのは「人的資本」であり、これは主に教育で作られた富ということだそうです。この結果が出たあと、ドイツや韓国は国としての教育費を上げたそうですが、日本は上げなかった。その後、日本は14位に落ちたそうです。
今、財政赤字が大きくドラスティックな投資ができない日本の現在で、これからの日本が大事にしていくべきことは2020年以降オリンピックが終わり景気がじわじわと落ちてもレガシーを見直しておけば日常の豊かさを確保できるのではないか、ということでした。
最後に聴衆の中から、「スポーツと文化をどういう接点を作っていけば良いか」という質問者に対しての講師のかたのお答えの中に「文化は当たり前の空気のようなもの」「知らず知らずに良いことをしている。それが文化」という言葉があり、ハッとしました。
会社でも、会社で努力していることで良いものはたくさんあり、それは当たり前であって、敢えて言葉になっているようなものではなかったりする。その「良さ」は、他の文化に触れて初めてはっきりと実感されるものです。
このたび、採用にあたり、わが社をどんな言葉で説明したらいいか話し合っていたのですが、敢えて声高に言わなくても、今大事にしていている文化のようなものかなと思い、その時に出てきた言葉が「会社の垣根を超えて技術というキーワードでみんなと繋がる」ということでした。できるだけ、技術者が交流する場に参加する、場を多く作る、知見を集約できる試みをする、など、事業継承をしてからというもの悩みながら取り組んできて、だんだんとそれが社員の人の手によって実現できるようになりました。
皆さんの所属する組織文化の良いところは何ですか?改めて周囲と話し合ってみると、意外と意識していない日ごろの良い文化に気付かされるのではないでしょうか。
みなさま、新年あけましておめでとうございます。
年末年始はいかがでしたでしょうか。私は…、忙しかった、に尽きます。
さて、早速ですが、仕事始めのミーティングでは「1on1(ワン・オン・ワン)」の話になりました。次年度以降どうしていくべきか。
「1on1」をご存知ないかたに説明しますと、ヤフーが導入して話題になったのですが、定期的に上司と部下が行う1対1の面談のことで、定期的に行うことによるさまざまな効果を狙うものです。
で、今年度は一人の管理職が数人の新人との「1on1」を続けてくれていたのですが、次年度以降はどうしていこうかと社内で検討中です。
そこで私自身がこれまで多くの部下の人と面談してきたときのことを振り返ってみたのですが、一対一での面談って、ものすごく難しいと思っています。
理由はいくつかありますが、まず、上司と部下はそもそも対等な関係ではないので本音を聞くことが難しいということ。あと、上司部下という非対等性を除いても言葉というツールを使いこなすのに長けている人とそうでない人では、言葉を挟んだコミュニケーションが対等にならないということ。人の変化や成長は、対話以外の要素がものすごく作用するので、対話そのものが変化や成長にどれだけ関わったかが見えにくいこと。
あと、昔の私は部下の人のしゃべる内容から部下の人の心情や直したいところを知り、成長の後押しをしてあげることができると信じていたのですよね。あることをきっかけに、それは不遜なことだと思うようになりました。
とある、仕事になかなか集中できず帰宅しても勉強ができないという悩みを持った男性社員と継続的に面談を重ねていた時のこと。当時、私は行動心理学の本などをたくさん読み、もしかしたら言葉の力で人を導くことができるのではと信じていました。
そこで、彼の悩みに対し、「私もこうだったけれど、こういうことを試してみたら上手く行ったよ」とか「こういうことができない心理背景にはこういう状況があるから、まずはそこを見つめるといいよ」とか、あるいは部下の悩みに役に立ちそうな本を貸してみたりしていました。
いつも憂鬱そうな表情の部下ですが、面談の場ではだんだんと表情が明るくなり「分かりました!やってみます!」と返事をしてくれます。ですが、数日して様子を見るとやはり辛そうにしている。またしばらくして面談するも、そのときは声が明るくなるけれど状況は変わらず、ということが続きました。
どうやら、解決の因果を分かり易く提示できるような事例で説明すると、その場では問題解決がすごくうまく行きそうに思えて少し気分が上がるのですが、日常に戻るとそんなに簡単には状況が変わるわけでもなく、私の言葉は一過性のカンフル剤的な作用しかなかったようです。家での勉強法についてとか、社内でのポジション変更とか、いろいろな角度で話し合ってみましたが、最終的に彼は転職していきました。
ただただ、私の未熟さゆえの失敗談です。あと、どうしても向いていない人と無理な改善の方向を探るよりは別の道を提示して背中を押してあげるのも必要ということでしょう。
今の私は代表ですので立場が強過ぎるため、直下の部下以外とは年に一度、全員との面談をする以外は別の管理職の人にお願いをしている形です。ただ、部下の人のほうから話しかけてくれるフックをいろいろと用意していきたいなと考えています。会社のWikiとかブログに実践で役立ちそうなことを書いたり、ノベルティグッズを通して各現場の喜びの声を報告してもらったり。なんというか、上から下へ何か言うとそれは圧が生まれてしまうので、下から上に細くても流れが作れるようなことがたくさん作りたいですね。
と、ちょっと否定的にも取れる書き方になってしまいましたが、実際には、我々の仕事は黙ってやる作業が多く、チームによってはコミュニケーションが不足することで大きなリスクを招いていることがあります。カジュアルに会話する訓練は絶対に必用だと思っています。そのためにもよく練られたガイドラインは必要ですね。
ということで、今年最初のエントリは「1on1」について書きました。それでは、本年もよろしくお願いいたします。